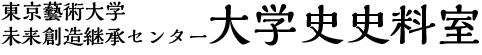『東京芸術大学百年史』は、本学創立百周年記念事業の一環として編纂されました。音楽学部では、昭和62年から平成16年にかけて『東京音楽学校篇』2巻、『音楽学部篇』1巻、『演奏会篇』3巻を刊行しました。このたび『東京音楽学校篇』第1巻のPDF複写版を公開しましたので、ぜひご活用ください。
“※公開にあたり公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団および株式会社音楽之友社に許諾をいただきました。
記して感謝申し上げます。”
東京音楽学校篇 第1巻(財団法人芸術研究振興財団/東京芸術大学百年史刊行委員会編、音楽之友社、昭和62年)
第1巻全体のPDFはこちら (236MB)
東京音楽学校篇 第2巻(財団法人芸術研究振興財団/東京芸術大学百年史刊行委員会編、音楽之友社、平成15年)
第2巻全体のPDFはこちら (1780MB)